 6月30日。
6月30日。7月1日。
両日は、小野照崎神社の「お山開き」です。
この神社には「富士」があるのです。
いわゆる「富士講」ですね。自然のものを使う場合もありますが、「富士塚」を築いて、そこに富士山の神様も祀っている、富士信仰の拠り所となっているものです。江戸の昔より信仰の厚いところだったのでしょうか。富士の本物の溶岩を持って来て積み上げたと言われる立派な富士塚があり、1年に2日だけ、この富士に登ることができます。頂上まで登れば、富士山頂まで行ったのと同じご利益がいただけると言われています。当然、毎年ここへ登らねば1年が収まらない感じがする昨今です。

 ところが、今年はたまたま土日にあたりました。
ところが、今年はたまたま土日にあたりました。まぁ、混んでる混んでる!
これは日にち指定なので、平日に当たる年は結構空いていて、日中自由な私たちは毎年信心深くお山に登りに行っていました。故に無病息災。疲れてはいるものの、大病もせず過ごせているのだろうなぁと思いますし、小野照崎神社も「学問」と「芸能」の神様ゆえ、ことあるたびに結構な頻度で参拝していますので、正式な氏子ではありませんが、もう自分のところの神社のような気分でいます。なにせ、数年前までは鳥居の真ん前に住んでいたのでね(笑)
でも、「マイ神社」を持っていることの安心感はハンパないものがあります。
なにをもってしても、きっと神様が見ててくれると。真面目にやって入れば、とんでもないことになるわけがない。そんな気分で、勇気を持って日々の仕事に邁進できるというものです。宗教家でもなんでもないですし、高校はキリスト教系の学校でしたが、なんとなく神社には安心感がありますね。
ちなみに、江戸七富士と言われる富士塚は、品川富士(品川神社境内)、千駄ヶ谷富士(鳩森八幡神社境)、江古田富士(茅原浅間神社境内)、十条富士(富士神社境内)、音羽富士(護国寺境内)、高松富士(富士浅間神社境内)、それに下谷坂本富士(小野照崎神社境内)なのだそうで、どちらも現存しているそうです。回ってみるのも一興かもしれませんね。

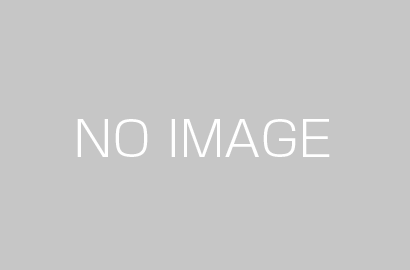



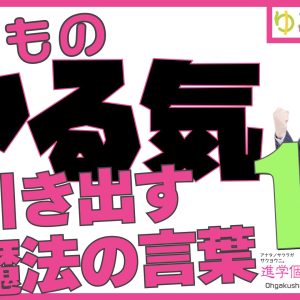



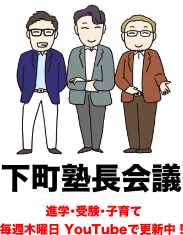
この記事へのコメントはありません。